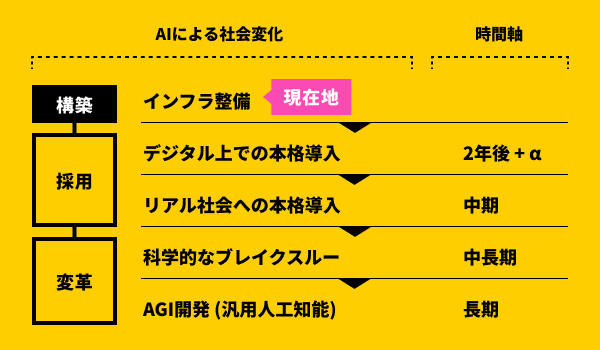*世界の経済成長率が3%を下回ると不況感が強まるとされる。ただし、デジタル経済で増している経済厚生(経済的幸福度)は成長率には反映されにくいので、見かけほど不況感は強まらない可能性もある。
*経済規模を示すGDPは1年間で生み出された付加価値額の総和になるが、デジタル経済で生み出されたサービスの大半は公共財に近い性質があるので、金銭的な数値には反映されにくい。
*コロナの影響で2020年の日本のGDPは落ち込んでいるが、消費者のお得感を示す消費者余剰は増えている。野村総研がネットの利用時間などを基に消費者余剰を試算したところ、2020年にデジタルサービスから生まれた消費者余剰の総額は日本全体で200兆円を超えている。16年時点では160兆円程度なので4年で25%ほど増えたことになる。2020年のGDPは16年比で2.4%減っているが、消費者余剰との合計では4%増加した計算が成り立つ。日々の生活の満足度が向上していれば、GDPの落ち込みほど豊かさは失っていないともいえる。
*GDPの算出で、データが生み出す価値を捉える取り組みが始まる。現在は、デジタルを使ったサービスや取引が広がっているにもかかわらず、データが生み出す価値を十分に捕捉できていない。今後はデータやデータベースの整備が設備投資として計上される。新基準を導入すれば日本の名目GDPは1~2%押し上げられるという試算がある。
*ブレークイーブン・インフレ率とは市場参加者のインフレ予想を反映する代表的な指標。通常の国債と物価連動国債の利回り差から算出する。ブレークイーブン・インフレ率は実質金利を算出するときなどに使われる。
<インフレ要因>
・人手不足で賃金が上昇している。米国においては求人件数が700万件程度まで減ると賃金上昇率が3%程度まで落ち、FRBの2%物価目標と整合するとされる。7月の求人件数は718万件と概ね整合する水準まで落ちてきた。有効求人倍率は1倍を割り込んだようなので、賃金の上昇は鈍化しそう(
9/4日経)。
ただし、米国で最大の求人プラットフォームを運営するIndeedは8月の決算説明で「求人広告数は減少が続いているが、米国の経済見通し改善を背景に5~6月は中小企業の求人需要に回復の兆しがみられた。米国の求人需要は今年度の下半期に底を打つ可能性が高い」と言っているので(
8/5日経)、再び賃金が上昇基調に戻る可能性もある。
・脱炭素シフトでエネルギー価格や資源価格が上昇している。脱炭素シフトにより2030年まで年0.7~1.0%程度の物価押し上げ効果が見込まれている。
*脱炭素シフトが完了すれば再生可能エネルギーは強力なデフレ圧力になる。
・財政拡張が物価を押し上げている。米国では積極財政が生んだ累積的な「財政ショック」が2023年の米インフレ率を0.5%押し上げたと推計されている。財政要因は直近の数四半期でも0.6~0.7%の押し上げ寄与があると推計されている。
*政府債務の増加は通貨の価値低下につながる。
・トランプ大統領の関税引き上げ政策もインフレ圧力になる可能性がある。米国の平均関税率が10%上昇すると、米国のインフレ率は25年に0.6%、26年に0.2%上昇するという試算もある。一方で、関税は消費税と同じで、消費者の購買意欲を削ぐ景気抑制的な政策なので、インフレ効果はないとの見方もある。
・トランプ大統領はFRBに利下げ圧力をかけ続けており、自身の意向に沿った人物を送り込んでもいる。かつて米国でニクソン政権が同じようなことをしたとき、インフレは3%から9%近辺まで急上昇し、その後高止まりしている。今後、FRBの独立性が揺らげば、インフレ再燃のリスクは高まる。
9/3日経、
9/3日経
・ウクライナや中東地域の戦争によってエネルギーコストが上昇しているが、足元では落ち着きつつある。
・異常気象や世界人口増、新興国の経済成長、バイオ燃料需要、肥料価格上昇、ウクライナ戦争などにより、食料価格が上昇傾向にある。農作物・肥料価格の先行指標である
農業ETFは高値圏で推移している。
・経済の脱グローバル化(グローバル化の再構築)で製造が自国生産にシフトし生産コストが上昇している。
・世界の生産年齢人口が2010年代にピークアウトしている。今後は労働者が減る一方で人口は増えるので供給が追いつかなくなる可能性がある。
・米欧でインフレやAIへの不安などからストライキが頻発している。
・株高による資産効果で消費が落ちにくくなっている。
・通貨の減価が続いている。対ゴールドでみたドルの評価は1971年のニクソンショックから下がり続け50年あまりで100分の1に落ち込んでいる。ドルの供給が膨らんだほか、基軸通貨に対する信頼が低下したことが背景にある。企業や家計が持つ現金など、すぐに使えるマネーを示す通貨供給量「M1」は同期間に80倍超に膨らんでいる。
<デフレ要因>
・世界各国の金利は平時と比べまだ高い水準にある。金利高は需要を減らす効果がある。
・経済のデジタルシフトが加速している。デジタル経済で登場している財やサービスは既存のものより便利で安価なものが多い。例えば、検索やSNSは無料で、ネット上では価格比較を簡単にできるため売り手は超過収益を得にくくなっている。スマホが登場してからはカメラやオーディオプレーヤー、電子辞書などが売れなくなっており、1億曲超をいつでも自由に聴けるSpotifyは月1080円で利用できる。複製コストゼロのデジタルソフトやシェアリングサービスの普及などもあり、価格は下がりやすくなっている。
*市場競争が起こっている財(商品・サービス)は、差異化が図れない場合、価格が限界費用(追加生産コスト)まで低下する性質がある。デジタル財は限界費用がゼロに近いので、競争が起きると価格がゼロに近づく。
・イノベーション(新結合・技術革新)が加速している。今はインターネットやAIにより、情報や人やモノの「新結合」が起こりやすくなっている。イノベーションも強力なデフレ圧力になる。
・AIやロボットを活用した産業の「自動化」により、生産コストが低下している。
・世界的に経済成長率が鈍化傾向にある。過去40年で米国の潜在成長率は3%前後から2%前後に低下している。
・富の集中が加速している。デジタル経済では資本やアイデアの出し手に富が集中しやすくなっている。富裕層の支出性向(収入に占める支出の割合)は低い。
・世界的に少子高齢化が進んでいる。子どもが減って高齢者が増えると総需要が減る。
・人手不足で成長力が低下している。
・米国やOPECの原油増産により、エネルギー価格が下がり始めている。
以上をまとめると、インフレは落ち着きつつあるが、人手不足や保護主義、環境規制、紛争、財政ショックなど影響で、以前のような超低インフレに戻る可能性は低い。米国のインフレ率は2025年に2.5%くらいになり、その後は2~3%で推移しそう。
日本においては、国力の低下から円安は止まりそうになく、円安の影響で2%程度のインフレが持続する可能性が高い。インフレが高進した場合はキャピタルフライトが加速し、さらに円安・インフレが進む可能性もある。とはいえ、日本は少子高齢化社会なので、需要の基調は弱い。インフレが進むとしても比較的穏やかなものになりそう。
超長期で考えると、世界ではエネルギー革命や材料革命、AI・ロボット革命が進み、超デフレ(無料社会)になる可能性がある。
■金利
・米国の政策金利は4.25%で、3ヶ月金利は3.98%、2年金利は3.65%、10年金利は4.18%、30年金利は4.77%になる。
・日本の政策金利は0.50%、2年金利は0.93%、10年金利は1.65%、30年金利は3.17%になる。
*名目金利からインフレ率を差し引いた実質金利は資金の流れを決める最大の材料になる。実質金利がマイナスの状態では、国債を買ったり銀行にお金を預けたりすると実質的に損をするので、株式や不動産、商品などに資金が流れやすくなる。逆に実質金利がプラスの状態では国債などの「無リスク資産」に資金が集まりやすくなる。現在、米国の実質金利はプラス圏にあり、「無リスク資産」に資金が流れやすくなっている。日本の実質金利はいまだマイナス圏にある。
*現在の債券は魅力的な水準まで利回りが高まっている。たとえばリスクのほとんどない米2年債は利回りが3.65%もある。その他の質の高い債券にも魅力的な利回りのものが多くなっている。今後利回りがさらに上がる可能性もあるが、急上昇期はすでに終わった可能性が高いので、株式などのリスク資産より、債券に資金が流れやすくなっている。
*投資家は企業が将来生み出すであろう利益から金利分を割り引いて企業価値を算出する。金利が上がると割り引く分が多くなり、将来の予想利益は減る。将来の利益創出期待が大きいグロース企業ほど割り引く分は多くなり、理論価値が下がりやすくなる。
*銀行は短期金利で資金を調達して、長期金利で企業などに貸し出して利ザヤを得る。しかし長短金利が逆転すると逆ザヤになるので融資が減る。その結果、企業の投資も減り景気が後退しやすくなる。
*景気拡大期の「良い長期金利上昇」では、株価も上昇する傾向がある。過去の例では長期金利上昇よりも政策金利を引き上げたときの方が株式市場へのネガティブな影響が大きい。
*景気拡大期終盤に金利が上昇すると、資金の流れが「借り入れ」から「返済」に転換し、資金の逆回転が起こる。過去のバブル崩壊は全てこの金利上昇がきっかけになっている。
*利上げ局面で中銀が利上げを停止すると市場は急速に利下げを織り込み始め、株高が続くことが多い。警戒が必要なのはその後になる。金利が高い中での株高は危うい株高となり、なにかのきっかけでショックが起こることが多い。過去を振り返っても、利上げ終了後は1年ほど株が上がり、「サブプライムローン」の破綻などがショックの引き金を引くことが多かった。過去の例では、「○○ショック」は懸念された箇所からではなく、疑いもしなかったところから起きている。今回米中銀は2023年9月頃から利上げを停止している。
・FRBの利上げ局面における株式相場は「1,金融緩和の終了を嫌気した調整」→「2,利上げ中盤にかけての良好なファンダメンタルズを好感した上昇」→「3,利上げ終盤の過度な引き締めを懸念した反落」→「4,利上げの打ち止めを好感した反発」→「5,ファンダメンタルズの悪化を織り込んだ大幅な下落」という経過をたどることが多い。今は4の局面でFRBは「予防的利下げ」をしている。一般に、このパターンは株価が上がりやすい。
■債務
・世界の債務はコロナ禍で急拡大し過去最高水準のGDP比336%に達している。ただし、コロナ禍の経済対策により、家計や企業、金融機関の財務状態はコロナ前よりも健全になっているためデフォルトが急に増える状況ではない。
・銀行の財務状態は比較的良好だが、銀行に比べて規制・監督体制の緩い「シャドーバンク(ノンバンク)」の債務は急拡大している。世界のファンドや年金基金、保険会社などノンバンクの金融資産は21年に239兆ドル(3京6000兆円)と07年比で2.4倍に増え、銀行を大きく上回っている。ノンバンクは信用力の低い企業へ融資することが多く、今後も融資は拡大していく見通し。ノンバンクによる企業向け融資(プライベートクレジット)は金融規制の対象外にあるためデフォルトリスクを把握しづらい。金利が高止まりし景気後退に陥ればデフォルト率が7%くらいまで上昇する可能性がある。
*プライベートクレジット事業者は2008年の金融危機後に設立されたところが多いため、デフォルトの影響は未知な部分が多い。
*銀行は預金者のお金を貸し出しているため、その資本は損失に備えて厳しい監視下に置かれている。一方、プライベート資産を運用するプライベート・デッド・ファンド(以下PD)は機関投資家から調達した資本そのものを貸し出しているので、規制は銀行に比べて緩い。銀行が破綻すれば預金者は保護されるが、PDが破綻しても機関投資家は保護されない。
*膨張するプライベートクレジットが将来の金融危機の火種になりかねないと、米証券取引委員会(SEC)など米国の金融当局者や著名エコノミストが警鐘を鳴らしている。2008年の金融危機以降に強化された銀行資本規制により、銀行発の金融危機再来のリスクは相対的に低下しており、システム全体にショックを波及させる潜在的な感染源はノンバンク融資にあるという。
*米国の金利の高止まりは、ノンバンク業界を直撃する。ノンバンクは通常、リスクの高い借り手に高い金利で貸し付ける。金利高止まりの影響で借り手の返済能力は落ち不良債権が増えている一方で、貸し手の資金調達コストは上がっている。ノンバンクでは時価会計を行っていない運用会社が多いため、問題があっても資金繰りが苦しくなるまでそれが表面化しないことが多い。商業用不動産市場では価格が半分になった例も珍しくない。高金利の下で経済に内在する不安定要素は増している。
・プライベートエクイティ(未公開株)ファンドでは投資回収が難しくなっている。PEファンドが抱える未売却企業は約2万8000社、3兆2000億ドル(約500兆円)相当に及ぶ。
・米金融市場では商業用不動産が大きな”爆弾”になっている。商業用不動産の10年間の価格上昇率は日本が20%なのに対し、米国は50%になっている。米国の商業用不動産向け貸出額は2010年から2023年まで約2倍に膨らんでいる(日本は同期間に3割増)。一方で、リモートワークの浸透や金融引き締めによるオフィス需要の低下によりオフィスの空室率は20%に迫っている。金利上昇により商業用不動産向けの融資基準は厳格になるなか、2024年に80兆円規模の償還期限が到来する。そこで借り換えができない場合、物件は市場で売却されるため、市場価格の調整圧力はかなり大きくなる。米欧ではGDPに占める商業用不動産の割合が1~2割に高まっているため、不動産バブルが崩壊すれば米経済は大きく下押しされる。米不動産ファンドは世界中に分散投資しているため、ファンドのリバランスで世界中の商用不動産に売りの連鎖が波及する恐れがある。
*2024年はそつなく借り換えが進んだもよう。次の山場は2026年以降になる。
足元で米商業用不動産を取り巻く環境はじわじわと悪化している。商業用不動産の中でもとりわけ深刻なのはオフィスビル。23年後半から融資のリスクが急激に顕在化し、30日以上返済延滞している案件の割合は過去10年で最悪となっている。商業用物件の取引数は、過去最低レベルで低空飛行中であり、今年後半以降に増加するローンの満期に耐えられるかどうか懸念されている。ただ、商業用不動産の貸し手は比較的小規模な銀行が多く、銀行の健全性は以前より格段に高まっているため、デフォルト率がある程度高まっても、銀行システム全体の危機に発展する可能性は低い。
住宅用不動産も”爆弾”になりつつある。金利の上昇に加え、保険料など維持費も上昇しており、空室率は高止まりしている。マンション向け融資残高は23年末に約2兆2000億ドル(約345兆円)と、焦げ付きが顕在化しつつある商業用不動産向け融資の6割に達している。マンション向け融資の延滞率は2024年1月に0.44%となり、リーマン危機の水準を上回り過去最高を更新している。リーマン危機の際には、延滞がピークに達してから貸し手の損失がピークに達するまでに約2年を要している。24年と25年には5000億ドル(71兆円)の融資が返済期限を迎える。借り換えに失敗すれば割安な価格で不動産を手放さざるを得ず、価格下落に拍車がかかる恐れがある。
・米政府の公的債務のGDP比率は07年の35%から22年には97%まで高まっており、53年には181%まで上昇する見込み。
・日本の超長期債の金利上昇が止まらない。これは財政膨張に歯止めがかからなくなるとの懸念があるため。英国のようにちょっとしたショックで金利上昇が加速し金融市場が混乱する可能性もある。
*金利が経済成長率を下回っている状態では、企業は財務レバレッジを効かせるだけで(低金利で社債を発行して自社株買いをするなど)で利益を手にすることができるため債務が膨らみやすくなる。政府も多少の財政赤字を続けていても債務残高のGDP比を一定の水準に維持できるので債務が膨らみやすくなる。
*今は企業がお金を借りて経済を牽引しなくなった分、政府がお金を借りて経済を下支えする構造になっている。政府がお金を借りて経済を下支えすると財政赤字は膨らむが、民間需要が足りていない中でそれをしないと、景気悪化を招き、財政赤字がさらに膨らみやすくなる。
*債務拡大ペースがGDPの成長速度を上回る状態が続くと、どこかで必ず資金の逆回転が起こる。債務拡大ペースはここ10年以上、毎年GDPの成長速度を上回っている。
・中国は2013年に労働人口がピークアウトしているので、今後は経済成長減速と同時に社会保障費が増加し、政府債務が膨張しやすくなる。2023年は過去最大の財政赤字(約74兆円、GDP比3%)を計上する見通し。
・22年6月の中国の非金融部門の債務残高はGDP比295%に達し、98年3月末の日本の296%と肩を並べている。
・中国は前例のない投資主導経済を20年にわたって続けている。過去40年間に消費のGDP比は53%から38%へ低下し、消費が投資を下回り続けている。この投資主導経済の実態はコスト先送りによる需要創造になる。多くの資産が健全資産とはいえず、不良資産が積み上がっている。
*一方、米国では労働者に購買力を与え、生活水準を向上させることで需要を創造してきた。過去40年間に米国の消費のGDP比は60%から68%に上昇している。
・新興国のドル建て債務の増加も著しく、10年前の約2倍(約500兆円)まで増えている。足元ではドル高が続いており実質的な返済負担が増している。一部の国ではデフォルト懸念が高まっており、デフォルトがいったん起きればドル高が一段と進み、デフォルトが連鎖しやすくなる。
・新興国の債務残高は22年3月に1京3000兆円とリーマン危機直後の4倍まで増えている。債務破綻の危機に直面する新興国が増えている。
<バブルについて>
バブルとは投資家が借金をして資産を買いまくることにより起こる現象。現在バブルは発生しているが、その投資主体は民間から政府(中央銀行)にシフトしているので、バブルは破裂しにくい。政府が資産を売却すればバブルは破裂するが、政府債務は実質的に返済不要なので資産を大きく売却する可能性は低い。足元で一部中銀はインフレ対策として資産の売却を進めてはいるが、インフレが落ち着けば売却をやめるので、”中銀バブル”が完全崩壊する可能性は低い。
■金融政策、財政政策
・世界の大部分の中央銀行は金融緩和に転じている。
*景気後退を予防する目的の利下げや、インフレが落ち着いた後に行う利下げでは株高が発生しやすい。一方、景気後退を伴う利下げでは株安が発生しやすくなる。
・日本の中央銀行は世界の大多数の中央銀行とは対照的にインフレ対策として金融引き締めをしている。ただし、国内需要は弱く、世界中の中銀は金融緩和に動いているので、金融引き締めは非常に穏やか。日銀のバランスシート膨張や政府債務の拡大も金融引き締めをしにくくしている。
・無借金経営企業が増え、家計の金融資産も増えているため、利上げの効果は一昔前とは変質している。金利が上がっても企業の利払いは昔ほど増えず、一方で家計の利子所得は増える。場合によっては、利上げがむしろ景気刺激的に働くこともある。民間の資産が大きいということは、それと表裏をなす政府の債務が大きいということになる。金利が上昇すれば政府の利払いが増え、その分だけ財政赤字は拡大するが、一方で、政府から民間にお金が渡ればその分だけ人びとの所得は増える。利上げにはこのような景気や物価を刺激する側面もある。それでも利上げの波及経路には為替や株価などもあるため、全体として利上げは物価抑制効果を持つと考えられている。しかし、政府債務が巨額になった分、今は昔よりずっと総需要押し上げ効果は大きいと考えられる。米国では0%から5%超まで利上げをしても経済はさほど減速していないが、その一因は政府の利払いにあった可能性がある。日本の政府債務はGDP比で米国の倍近くあるので、日銀が利上げを進めたとき、十分な物価抑制効果が得られない可能性がある。利上げの効きが悪ければさらに利上げをしなければならないという悪循環のリスクがある。巨額の政府債務が当たり前となった現代において、利上げがインフレ抑制に効かなくなりつつある。
4/18日経
*米国や日本は現在、財政赤字拡大を容認する現代貨幣理論(MMT)のような金融・財政政策をしているが、歴史的には中銀の貨幣発行によって財政赤字の穴埋めをしてきた国は、インフレを制御できなくなり、投資や成長が著しく落ち込むという結果に終わっている。
*MMTとは自国通貨で借金ができる国は破産することがなく、高インフレを招かない限りは財政支出のしすぎを心配しなくてよいという政策。提唱者のケルトン教授によると、財政支出を拡大してインフラや教育、研究開発に投資すれば長期的に国の潜在成長率を高めることができ、財政赤字を縮小できるという。高インフレ問題についてはインフレ防止条項(増税など)を入れておけば問題ないという。
*MMTで潜在成長率を高められなかった場合は、膨張した政府債務を国民が増税や高インフレで負担しなければならない。
*MMTで高インフレになった場合、中銀は金利をあまり引き上げられない。中銀のバランスシートの質はすでに劣化しており、そこで金利を上げたら自己資本がさらに劣化し、さらに金利が上昇するという悪循環に陥ってしまう。日銀は政策金利を1%まで上げると2年程度で債務超過に陥るとされる。FRBは政策金利を3.0~3.8%まで上げると金利収支が「逆ざや」に転じるとされる。ECBも金利引き上げにより財務状態が危機的な水準に陥る可能性が高い。
*MMTは日本が行っている金融・財政政策とは若干異なる。MMTは財政再建を重視せず、中央銀行を政府の支配下に置くが、日本の政策の場合は、政府は一応は財政再建を目指し、中央銀行は政府から独立している。
■政治
・日本の政治は比較的安定しているが、財政収支は悪化の一途なので、長期の見通しは悪い。
・海外の政治は不安定。ただウクライナや中東地域の紛争は落ち着きつつある。
・米国では資本主義と自己責任社会の帰結として、格差拡大が続いており、民主主義が機能不全に陥りつつある。
・米国と中国の覇権争いは、ハイテク・軍事分野を中心に長期にわたり続きそう。
・米国は典型的な衰退期に入ったという見方もある。マクロ分析の専門家であるレイ・ダリオ氏は、国家のサイクルは「新たな秩序が始まって政府の官僚制が整うステージ」「平和と繁栄を迎え支出と債務が過剰になるステージ」「財政状況が悪化し内戦、革命に向かうステージ」の3つのステージに分けられ、現在の米国は衰退期に属する3つ目のステージに入ったと言っている。
・中国は政府が「共同富裕」のスローガンを掲げ規制を強化しているので、民間の活力がそがれつつある。国外からの投資も、各種規制やスパイ法などの影響で著しく減っている。この調子でいくと中長期でも経済成長が減速していく可能性が高い。中国共産党が一党支配を最優先する限り、この傾向は続き、最終的に中国はロシアのような国になる可能性がある。
*23年の海外勢の対中直接投資額は21年の51兆円の1割程度まで落ち込んでいる。
・中国経済がかつての日本のようなデフレに陥りつつあるという見方が強まっている。日本は1990年代から不良債権、雇用、設備の3つの過剰に悩まされた。中国も今同じ3つの過剰に悩まされている。当時の日本は欧米市場へのアクセスが確保され、海外に活路を求められた。しかし今の中国は米国と対立し、欧州でも中国製EVを締め出す動きが広がっている。米欧の半導体輸出規制により先端半導体の調達にも支障をきたしており、技術的にも追い詰められつつある。
・レイ・ダリオ氏は「中国は今後100年間続く嵐に突入しつつある。バブルが崩壊し、試練が続くだろう」と言っている。
・EUは域内で財務格差が広がりつつあるが、コロナ危機やウクライナ戦争などの危機でEU加盟国の結束は強まっており、政治は比較的安定している。
■その他の景気後退シグナル
・米景気の先行指標である
米住宅着工件数はピークアウトしているが依然高水準にある。
*景気拡大期の終盤に入ると、消費者はまず住宅や自動車などの大型耐久消費財の購入を手控えるようになる。
・米個人消費の先行指標である9月の
消費者信頼感指数は97とまあまあ堅調な水準にある。同指数が80を下回ると景気後退のリスクが高まる。
*米GDPの約7割は個人消費が占める。
*ISM指数やPMI指数が45を下回るか、50割れの期間が半年を超えるとデフォルトが増えやすくなる。
・
ユーロ圏のPMIは49.5と中立の水準。好不況の分かれ目である50を2年以上下回っていたが、8月に50.5に浮上している。
・世界景気の先行指標である
中国製造業PMIは49.4とほぼ中立な水準。基調としては横ばい傾向。
・
米国の失業率は低位で推移しており現在4.3%。「完全雇用(3.5%)」に近い水準にある。
*米国では失業率が前年同月と比べて0.25%上がると景気後退に陥りやすくなる。8月の失業率は前年同月を0.1%上回っている。
*米国では直近3ヶ月の平均失業率が過去1年の最低値を0.5ポイント上回ると景気後退に陥りやすくなる。現在は0.2ポイント上回っている。
*米失業率が「完全雇用」の水準まで下がると賃金上昇により企業収益が圧迫され、労働力不足で経済成長は頭打ちになる。
*米株が安定的な回復基調になるのは失業率がピークを打って低下し始めた後になる。
・経済危機をいち早く察知する
米低格付け債の利回りは底打ちして持ち直しつつある。
・米国で「長短金利の逆転」「
社債スプレッド(社債利回りと国債利回りとの差)の拡大」「物価上昇」のうち、2つが起きたら景気後退に陥るとされる。つい最近まで3つ起きていた。現在は1つ。
*社債スプレッドが1%増加すると株式を7%下落させる効果があるとされる。
■その他の株式シグナル
・
米個人投資家の心理は株価の先行指標になる。個人投資家の心理は株式市場の「逆指標」になるとされ、「悲観」の場合は大底、「楽観」の場合は天井を示唆することが多い。この指標が「異常な弱気」を付けた後の6~12ヶ月は平均以上の株価上昇になりやすい。現在は「中立」の水準。
・
ブルベア指数も米個人投資家の心理を示し、株価の先行指標になる。現在は-0.6%とほぼ「中立」の水準。
・
投資家の強欲と恐怖指数も株価の先行指標になる。この指標が「Extreme Fear(極度の恐怖)」となっている場合は、すでに株価にほぼすべての悪材料が織り込まれていることが多く、株価は好材料に反発しやすい。現在は52で「中立」の水準。
・機関投資家の運用資産に占める現金比率も株価の先行指標になる。この比率が4%を下回ると「株売りシグナル」になる。8月の現金比率は3.9%。
8/12日経
・
米VIX指数(変動率指数、別名「恐怖指数」)も株価の先行指標になる。この指標が低位にある場合は「楽観」を意味し、株価が上昇しやすくなる。しかし、低位の状態が続くと投機的売買が盛んになり、その後なんらかのショックで株価が急落することが多い。現在のVIX指数は16と低い水準にある。
・
スキュー指数も株価の先行指標になる。この指数は、S&P500種株価指数のオプション市場で、株価の上昇を見込むコール(買う権利)に対して下落に備えるプット(売る権利)の需要が高まると上昇する。これは市場で将来の大きな価格変動に備える取引が増えていることを意味する。2月18日には183と過去最高値を付けた。2021年のパターンでは、半年ほど後にS&P500指数は下落に転じ、1年半ほど調整している。現在のスキュー指数は145とやや高い水準。
・1871年以降の米国の平均的な景気後退期間は16.7ヶ月になる。株式は景気に6ヶ月先行するので、景気後退が始まって10ヶ月くらいたった頃が仕込み時になる。
・景気後退入りすると最初の数ヶ月間に株価が大きく下落する傾向がある。景気後退入りして最初の4ヶ月間のどこかで株式を買った場合、その後6ヶ月間のリターンはマイナスに終わることが多い。景気後退入りから5~14ヶ月の間に株式を買った場合は、その後6ヶ月の投資リターンはプラスになりやすい。
■その他の指標
・日経平均の騰落レシオは109とやや過熱の水準。
・日本株の信用評価損益率は-6.22%とやや過熱の水準。
・先進国の株価チャートは、軒並み最高値を突破しており基調は強い。
<NASDAQの10年チャート> 移動平均線との乖離率が高いのは気になるが、出来高を増やしながら上昇が加速している。今後さらに上昇しそうな雰囲気がある。